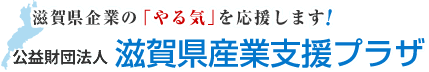2018-03-01
比良比叡トレイル ルート調査【4区間目 途中越え~打見山】
ルート調査この区間はトレイル調査の一番重要なところであった。一般に知られた登山道はなく、比良と比叡をどうつなぐか?いったん途中へ降りるか、稜線でつなぐか? 未知のことも多かったからだ。いくつかの案をもとに調査を試みた。
1回目は2016年11月12日。3人で花折峠から途中越えまで一部京都との境を稜線沿いに行く調査。比良の南端にある権現山から途中峠へいかにつなげるかの基礎調査だった。花折峠から歩き始める。入り口が少しわかりにくいがP812までは順調でそこで昼食。問題はそこからだった。道が不明瞭でルートを見失った。注意していながらも急な下りに導かれてしまう。3人で協議しながら苦労して復帰。そのあとも不明瞭な分岐をなんとかしのぎ、途中越えへ。最後の急坂も問題を残すコースだった。

20161112 花折峠西の稜線で
2回目は12月10日。5名で実施。権現谷からズコノバンへ上り、アラキ峠へ出て折立山から花折峠への道を探るというものだった。まず権現谷から権現山―霊仙山稜線へとりつくための枝尾根を上る。一応作業道がついているが、途中から不明瞭になる。稜線を外さずに登って、なんとか稜線に出た。このころからみぞれが降りだし、ズコノバンに着いたときは一面白くなっているところもあった。ズコノバンからは水平道をアラキ峠へ向かって進む。左手は急な谷に落ち込んでいる古道であったが1カ所崩落しており高巻きしてやりすごす。途中でっぱりの場所で昼休憩。休憩後アラキ峠へ向かって登るが、峠の手前で再度崩落地あり、注意して進む。さらに谷を詰めてほどなくアラキ峠に到着。写真だけとって折立山へ登り、北東方向の尾根から花折峠へおりた。下り道も不明瞭でどこが道かわからなかったが、およその方向とテープを頼りに峠へ下りた。

20161210 アラキ峠から折立の途中
3回目は1月7日。還来神社向かいから西の林道を小出石に上るルートを調査した。林道は以前までの様子とは大きく変わり、谷筋に土管を通して簡易な橋にされていた部分はすべて崩壊、徒歩でも渡渉が困難と思えるほど深くえぐられている。また上部の道は完全に消失していた。結果、急斜面を直登しなければならず、現状のままでは一般のトレイルとして使うには無理な状態だとわかった。稜線に上った後は、倒木や道荒れはあるものの歩けないことはなく、かすかに残る道跡をピークまで辿ることができた。下りも気を抜くと道を見失う状況で、道間違いを起こした。トレイルに使うには、不適と思われた。
4回目は2017年7月18日。3人で実施。途中越えから花折峠へのルートを南から北向きコースでの調査を行った。特に問題となったのはP812までのルート。逆向きでもやはり上り始めの急坂、p812手前の難路が大いに問題となり、不適との判断をせざるを得なかった。P812で折り返し、帰路県境ルートで下る。

20170718 途中峠から北向きに県境を
5回目は7月24日。2人で実施。再び権現谷からの上りを試みる。この回は霊仙山の扱いをどうするかが課題だった。稜線にとりついたあと権現山に行くには、そこだけ往復する必要があったからだ。特に下りにいいコースがあれば標準候補に加えたかった。霊仙山からの下り道をメインに調査する。霊仙山までは特に問題なくいけた。しかし、新たな下り道は狭く相当に急で、最後が谷へ落ち込み不適だった。霊仙山へ行くことはオプション扱いとすることとした。

20170724 霊仙山頂からの急な下り道
6回目は8月16日。途中から権現谷を経て打見山へ行くコースを通しで歩いてもらうこととした。4人で実施、うち一人は打見山から蓬莱へ。特に大きな問題はなく終了。
7回目は非公式なもので、朽木地区の調査予定が雨で変更となり、急遽途中まで戻って実施したものだが、権現谷から何とか脇の林道を使って霊仙山を巻き、頂上まで一筆でつなげないかという意図で調査した。以前下りで試みたリベンジでもあった。コースは権現谷の途中から舗装された脇の林道へ入り、南東の尾根から霊仙頂上へ行けないか、というもの。結果、林道終点からの道が判然とせず、断念せざるをえなかったが、うまく尾根を使えば行けるかもという期待は持てた。以後の魅力的な課題となった。

 © 青木繁
© 青木繁
 (日本語) アキギリ
(日本語) アキギリ
 (日本語) ギンリョウソウモドキ
(日本語) ギンリョウソウモドキ
 (日本語) オオイワカガミ
(日本語) オオイワカガミ
 (日本語) オオバアサガラ
(日本語) オオバアサガラ
 (日本語) キタヤマブシ
(日本語) キタヤマブシ
 (日本語) ギンリョウソウ
(日本語) ギンリョウソウ
 (日本語) コアジサイ
(日本語) コアジサイ
 (日本語) キンラン
(日本語) キンラン
 (日本語) シャクナゲ
(日本語) シャクナゲ
 (日本語) ショウジョウバカマ
(日本語) ショウジョウバカマ
 (日本語) タニウツギ
(日本語) タニウツギ
 (日本語) ナツエビネ
(日本語) ナツエビネ
 (日本語) ホウノキ
(日本語) ホウノキ
 (日本語) ヒメシャガ
(日本語) ヒメシャガ
 (日本語) タムシバ
(日本語) タムシバ
 (日本語) ヤマシャクヤク
(日本語) ヤマシャクヤク
 (日本語) ヤマツツジ
(日本語) ヤマツツジ